史跡を訪ねる
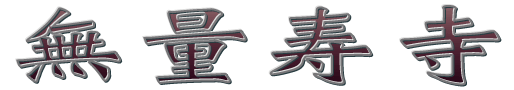
むりょうじゅじ
無量寿寺・解説文 |
|
本解説にあたり、無量寿寺住職婦人、無量寿寺婦人会々長、鉾田市史編さん室、の方々のご協力を戴きました。
また、参考文献は次の通りです。 【拾遺古徳伝絵】・【七瀬1】・【七瀬2】 【無量寿寺・名の由来】 無量寿寺は、大同元年(806年)に草創された、三輪宗の寺であり、その後禅宗となって無量寺と称していた。 時代は下つて、当地の領主・村田実刑部少輔平の高時の妻19歳にして難産の為、むなしく亡くなり当時の境内に 埋葬した。がしかし、愛着の念が消えず毎夜迷いの姿を現し、幽霊として現れ村人に恐ろしい思いをさせていた。 寺も荒れ果て、困り果てた村人は、親鸞を招き、救いを求める。領主・高時をはじめ村人一同迷魂の供養をしようと 明師を尋ねると、幸いに親鸞聖人が稲田から鹿島神宮へ御参詣の折にて、青柳より鳥栖を通ると分かり、待ち受け ていたところ、親鸞聖人が弟子の順信房を伴って来られた。御済度を願って親鸞聖人の許諾を得、多数の小石を 拾い集めるよう仰せつかった。すると、親鸞は、小石に浄土三部経二万六千六百余の経文を書き写した。 いわゆる一字一石経である。 それらの石をかの女性の墓に埋めると異変も止み、その女性は極楽へ往生できたという。 親鸞はこの寺に三年間住み、阿弥陀仏の像を自ら刻んで本尊とし、無量寿仏(阿弥陀仏)の名にちなんで「寿」の 一字を加え、無量寺を無量寿寺に改めた。 【菩提樹】ぼだいじゅ 樹齢800年 桑科植物 東印度原産 佛教では一切の諸佛の菩提を成就したる道場の樹として釈迦牟尼世尊も其の樹下に座して成佛大悟されたりと云う 此の樹は、親鸞聖人が無量壽寺在住の際、念珠を播かれたものと傅えられる。覚如上人は次の歌を詠んでいる。 「皆人菩提のこころおこせよと、植えたまえたる木こそとふとき」
【重要文化財目録標】
◇国指定重要文化財(国寶) 絹本着色拾遺古徳伝絵 絵 土佐光信 筆 本願寺覚如上人 ◇県指定重要文化財(建造物) 無量寿寺本堂 無量寿寺大門 無量寿寺鐘楼 ◇有形文化財御文章 本願寺実如上人筆 ◇天然記念物菩提樹 親鸞聖人御手植 ◇町指定文化財 無量寿寺樹叢 女人成佛経石塚 他、法宝物傅来 【拾遺古徳伝絵】しゅういことくでんえ
十四世紀初め、鎌倉時代の後期に作られた絵巻物で紙本着色(紙の上に描かれていて色絵具で塗られていること) 縦0.403m 横19.798mにおよぶ。 浄土真宗の勢力である鹿島門人の要請で、浄土真宗を開いた親鸞聖人の師、法然の伝記を題材とし、親鸞の曾孫 にあたる覚如により、伝記の文が作られた。これに、絵が付けられて成立したのが、本絵巻である。おそらく京都で 作られたものであろう。 全9〜10巻のうち、1608年にかなりの部分が焼失し、残りの部分で1巻に作り直された。 拾遺古徳伝とは、すぐれた先師の伝記のなかで洩れて残った部分を拾い集めたもの、という事。 【御佛供井】おぶくい
親鸞聖人自ら水を汲み給えし井戸あり、御在世より、水の増減更になく浄水湧出す、これを御佛供井戸と称す、 とあり次の歌が詠まれている。 「民草をめぐむこころの深ければ、あまねくあふげ法の真清水」
親鸞聖人が自らこの井戸水を汲み、仏前に供えて女人成仏を祈ったものと、言い伝えられている。
【親鸞聖人】しんらんしょうにん (1173〜1282年) 親鸞は承安3年(1173年)朝廷の皇太后宮大進という役職にあった日野有範の子に生まれたと伝えられている。 緒系図などを勘案すれば、中級程度の貴族の家柄であったようである。日野有範は何らかの理由で早い時期に 出家した。 まだ十歳にならない親鸞を頭として、五人に男子が残され、親鸞は伯父範網の導きにより、比叡山で出家して いる。 親鸞、29歳のときに比叡山を離れ、やがて法然のもとに入門した。多くの法然の弟子の中で、いち早く頭角を あらわしたが、しかし既成教団からの弾圧がすでに始まっており、彼らは朝廷を動かし、承元元年(1207年)には 法然以下が死罪・流罪にされるに至った。 越後國の国府(新潟県上越市)に流された親鸞は、この地で豪族・三善為教の娘である恵信尼と結婚した。 親鸞は、2、3年を越後で過ごした後、健保2年(1214年)一家で関東に移住する。 移住の途中、上野国佐貫(群馬県板倉町)、常陸の国下妻の幸井の郷(茨城県下妻市)茨城県笠間市の稲田、 で二十年間にわたる布教活動を始めた。稲田において多くの弟子や信徒を育てた。 また稲田から、石岡、八郷、小川、玉造、鹿島へ出向いて、布教活動を行った。 無量寿寺は、親鸞を招いて禅の寺を真宗の寺としたものである。 3年間在住の後、離別の際に当寺を託した鹿島順信房へ宛てて、次の御筆を執られた。 「別れ路をさのみなげくな法の友、又あふ国のあるとおもえば」
【幽霊図】ゆうれいず 作者不詳。寺の由来に鑑みて、相当の時期に、関係者により作製されたものと思われます。 無量寿寺といえば「幽霊の絵がある」ことで有名です。 【樹叢】 寺境内に密生している、数々の植物群。遊歩道が整備されているので、のんびりと、 野草散策が楽しめる。 【ケヤキの大木】 歴住大和尚の墓地にそびえる天然記念物。 【斑入りイチョウ】 イチョウの葉に斑が入っている珍しい種類で、天然記念物。 【焼 榧】やけがや
親鸞聖人が35歳の時、「変成男子の誓願空しからぬ女人成仏の証拠なり、必ず大悲を疑ふまじ」と仰せ られ、尚末世の為にとて焼きたる「かや」の実が成長したもの。 親鸞聖人が焼いた榧の実を播いたところ半分黒く焦げたような実を付けることから「焼榧」とよばれる。 平成13年4月22日に無量寿寺を訪問した時に採取した「かやの実」
 写真左:左半分の色に対し、右半分の色は黒く焦げたようになっています 写真右:表皮が乾燥した状態で残っていて、この表皮を剥くと左図になる 【女人成佛御経石塚】じょにんじょうぶつおきょういしづか 幽霊御済度の墳墓。【無量寿寺・名の由来】にあるように、御済度を願って親鸞聖人の許諾を得、信徒たちは
多数の小石を拾い集めるよう仰せつかった。すると、親鸞は、小石に浄土三部経二万六千六百余の経文を書き 写し、亡くなった女性の成仏を願ってお経を読み、それらの石をかの女性の墓に埋めた。すると異変も止み、 その女性は極楽へ往生できたといういわれのある塚である。 |
引き続きご案内
▼
▼
| 無量寿寺墓地 |
by ライフステージ
TOPページへ サイトマップへ